2006年09月07日
ぼくはマンガ家
手塚治虫/2000年/角川書店/文庫
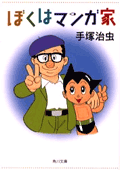 何でもっと早くこれを読まなかったのだろう?
何でもっと早くこれを読まなかったのだろう?
手塚治虫さんの自伝的な内容とその周辺の漫画史が軽快な調子で書かれている。読者を意識したユーモアがタップリで、ゴーストライターが書いたにせよ、本人が書いたにせよ読み応えのある本だった。
手塚治虫さんが漫画の中に映画的手法を構図に取り入れたのは、学生時代に見たフランスやドイツの映画だと書かれている。戦中に公開されていたドイツ映画はプロパガンダ映画の類も含まれており、もしかするとレニ・リーフェンシュタールの『美の祭典』とか『民族の祭典』あたりを見て触発されるところがあったのかもしれない。
恥ずかしながら、白土三平さんが画家の岡本唐貴さんの息子だったことも今回初めて知った。さいとうたかをさんのエピソードとかキューブリックからの手紙とか、もちろんトキワグループの面々の話など、凄い話が次々と出てくる。さすがは天才漫画家の生涯。
他にもアニメの話とか福井英一さんの死とか、いろいろ内容盛りだくさんで、とりわけ30年代の悪書追放運動以後の状況について書かれた文章が印象に残った。
いまでは、おとなが子供漫画を「芸術論」ふうに分析したり、批評したりして喜んでいいる向きもある。おとなが子どものおもちゃをとりあげたように。
(中略)
ぼくは現在こそ、野放しの漫画が非難され弾劾される時期だと思うのだが、あの当時の鼻息の荒い連中はどこへ行ってしまったのだろうか?(中略)ぼくらは、なまじ子供漫画芸術論をふりかざして擁護したもらうより、今一度、子供漫画のルネッサンスを期待して、徹底した批判を受けたい。
自分の漫画が時代遅れになっていることへの焦りと考える人もいるかもしれない。僕は文章のとおりに受け取りたいと思う。奥付は2000年になっているものの、この本が最初に出たのは1969年。今から37年前に書かれた文章である。「手塚の円環」だろうが「テヅカ・イズ・デッド」だろうが、結局のところ今も昔もこのあたりの問題は解決されずに残っているのだ。ポストモダン以降の状況って、本当にいろいろ面倒臭い。
Posted by Syun Osawa at 01:16