2011年09月15日
g2 vol.7
石井光太、安田浩一、久坂部羊 他/2010年/講談社/A5
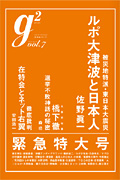 安田浩一氏の「ネット右翼に対する宣戦布告」という記事が載っていたので、『 g2 vol.6 』に続いて7号も買った。6号は数本の記事以外は相当つまらなかったけど、今号は逆にかなり面白かった。やっぱ石井光太氏とかが載っているとグッと深い感じの誌面になっていいですな。
安田浩一氏の「ネット右翼に対する宣戦布告」という記事が載っていたので、『 g2 vol.6 』に続いて7号も買った。6号は数本の記事以外は相当つまらなかったけど、今号は逆にかなり面白かった。やっぱ石井光太氏とかが載っているとグッと深い感じの誌面になっていいですな。
特に面白かったのが、久坂部羊「熱血医学教室」、石井光太「人を殺した子どもたち」、夏目幸明「マグロの守護神たち」など。どれもバラエティに富んでいて、一本一本それなりの深さがある。ネットの浅い情報を追いすぎている僕には、このくらいの深さがとても心地よく感じられる。
ネット右翼関連の話については、ニコ動、ニコ生、2chなどで繰り返されるヘイトスピーチが、なぜなくならないのか? ということについて、今回の文章を読んでもわからないままだった。ただ、コミュニタリアン的な思考を通して彼らの活動を見たとき、そこにある問題というのは、決して僕とは無関係ではないということも思うようになっている。このシリーズはネットでも食いつきのいいトピックなので、できればシリーズ化してほしい。
Posted by Syun Osawa at 02:07
ポーキーズ
監督:ボブ・クラーク/1981年/アメリカ
 30年前の青春エロコメディ映画。ここ最近たて続けに見ているこのジャンルの作品の中では、かなり古い作品で、しかも作品自体が50年代のフロリダの高校生を描いている。
30年前の青春エロコメディ映画。ここ最近たて続けに見ているこのジャンルの作品の中では、かなり古い作品で、しかも作品自体が50年代のフロリダの高校生を描いている。
現在の高校生像を描いた近作と比べると、昔の高校生活には、街のコミュニティがしっかりとあることに気づかされる。今は、家族と学校の間に何もない。『ポーキーズ』の頃のアメリカも郊外化の問題は抱えているものの、映画の中では家族と学校の間に街のコミュニティがあり、そこで起きる事件がストーリーを引っ張っていた。
南部の話(ニガーという呼称)、ユダヤ(カイクという呼称)などの問題も出てきて、エロコメディでありながら社会(ここではコミュニティと言った方がいいのかな?)が自然と意識させれてしまうところが、時代だなと。
でもやってることは、セックスの話で、そこは全然変わらないんだけどねw
Posted by Syun Osawa at 02:04
やめないよ
三浦知良/2011年/新潮社/新書
 震災の後にあったチャリティゲームで、Jリーグ選抜として出場したカズがゴールを決めた。おっさんなら誰しも感動しただろうこのシーンのすぐ後に読み始めたもんだから、タイトルの「やめないよ」ですでにご飯3杯いける感じだった。
震災の後にあったチャリティゲームで、Jリーグ選抜として出場したカズがゴールを決めた。おっさんなら誰しも感動しただろうこのシーンのすぐ後に読み始めたもんだから、タイトルの「やめないよ」ですでにご飯3杯いける感じだった。
とはいえ、この本には胸を打つようなモチベーションを上げる言葉が埋め尽くされているわけではない。むしろ、現役選手としてどう日々すごしていけばいいかという実戦的なことが書かれている。僕はそのことに、さらに感動した。
例えば、日本の侍の精神論を説いた『葉隠』は、平和な時代を生きた山本常朝によって書かれた。その一方で、戦闘に明け暮れた宮本武蔵やチェ・ゲバラは『五輪書』や『ゲバラ日記』などの実戦的な書物を残している。カズが書いたこの本は後者のタイプで、懐古的な精神論に浸るのではなく、中年になった今のカズがプロとしてどのようにあるべきかを綴っていた。まさに、戦う男の書いた本だった。
だから、本を読み終えた後、『やめないよ』というタイトルの言葉が、さらに強さを増して僕の胸に押し寄せてきた。そして、お前はどうなんだ? と続けて問われた気がして、少し苦しくなった。
Posted by Syun Osawa at 01:58
コミュニティを問い直す
広井良典/2009年/筑摩書房/新書
 自分の中の関心トピックである「コミュニティ」についてお勉強。前に読んだジェラード・デランティの『 コミュニティ ― グローバル化と社会理論の変容 』はイギリスの学者から見たコミュニティの話だったので、日本人が書いたコミュニティ本を今回は選んでみた。
自分の中の関心トピックである「コミュニティ」についてお勉強。前に読んだジェラード・デランティの『 コミュニティ ― グローバル化と社会理論の変容 』はイギリスの学者から見たコミュニティの話だったので、日本人が書いたコミュニティ本を今回は選んでみた。
この本では、日本特有の「場の空気」について言及されている。ちまたで「空気を読め」とか「空気が読めない」などという風に使われるこの「空気」というものは、互いに同意できるコミュニティがそこにあることが前提となっている。そして、このコミュティの内部では過剰なほど周りに気を使ったり同調的な行動が求められる一方で、一歩でもその集団を離れると誰も助けてくれる人がいない(孤立化、ぼっち化)といった「ウチとソト」の落差の問題を抱えている。著者は、このことが生きづらさにつながっているのではないかと問う。
また、地方の高齢化とコミュニティ破壊の問題も深刻だ。著者はシャッター街と化した地方都市に若者を呼び戻し、そこに再びコミュニティを構築するアイディアを披露しているが、地方の快適な空間や自然環境だけでは、若者が地方に戻ることはないだろう。なぜなら、今は地方も都会も並んでいる店にほとんど差がないため、若者にとっては人の数が多いかどうか、交通の利便性といったシンプルな動機がその場所に留まる条件になりやすいと思うからである。これは、最近の日本総郊外化の問題そのものである。
だから、地方と都市は相互補完的で対等な存在では全然ないのだ。よって、人の少ないその場所に留まるべき積極的な理由がなければ、地方のコミュニティは破壊され続けるのだろう。もちろんその一方で、都市にはそもそも強いコミュニティが存在しないわけで、これはなかなか大変な問題だなと、この本を読みながらぼんやりと考えていた。
結局のところ、日本におけるコミュニティの問題は、上に書いた関係の二重性(ウチとソトの問題)と、中間共同体(集団)をどうつくるかという問題に集約されているように思うし、これは、誰もが感じているところだろう。著者は、そのどちらも必要で、それらが相互補完的なコミュニティを構築するべきだと言っており、これには同意できる。
とはいえ、農村型コミュニティを復活させようというようなことは難しい。今だと突破口はネットということになるのだろうが、ネットの最大の問題は距離の壁を越えられないということで、その点について何かもう一歩踏み込んだコミュニティ像が示されれば、僕のようなお一人様のおっさんも少しは未来に対する不安が軽減されるのだと思う。
Posted by Syun Osawa at 01:54
2011年09月07日
40cmの童貞男
監督:ニック・ガイタジス/2006年/アメリカ
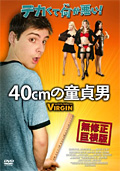 原題はたぶん全然違うのだろう。調べてみたら、案の定「Gettin' It」だった。『 40歳の童貞男 』がヒットしたので、紛らわしいタイトルにして釣り上げようという魂胆だったのだろうが、さすがにこれは似すぎている。僕も間違って借りてしまったじゃないかw
原題はたぶん全然違うのだろう。調べてみたら、案の定「Gettin' It」だった。『 40歳の童貞男 』がヒットしたので、紛らわしいタイトルにして釣り上げようという魂胆だったのだろうが、さすがにこれは似すぎている。僕も間違って借りてしまったじゃないかw
結論から先に言えば、『 40歳の童貞男 』には遠く及ばない代物だった。主人公にいきなり可愛い彼女がいる時点でワクワク感がない。唯一の困難といっても彼女にセックスしたい気持ちがないことくらい。
一応、チンコがでかすぎるというのが作品の主題にはなっているのだが、それを生かす場面も少ない。童貞もあっさり喪失するし、そこに対するカタルシスがあるわけもない。これはエロに限らないことだと思うが、エンターテイメント作品というのはピンチの演出にあると信じているし、これは宮崎駿大先生が昔、インタビューで力説していたことでもある。フックになるはずの40cmのチンコや童貞喪失という壁が、わりと簡単に乗り越えられて、ハーレム状態になっているところに物足りなさを感じずにはいられなかった。
コンドームの大きさからチンコのでかさを連想させる「ジョーズ」的な演出とか、40cmという大きさが実は違ったというオチなど、ネタ的に良いところもたくさんあっただけに、ご都合主義のプロットがただただ残念。アルバトロス系の作品とかが好きな人は、逆にこういうのが好きなのかもしれないけどね。
Posted by Syun Osawa at 00:58