2005年04月30日
気まぐれオレンジロード あの日にかえりたい
監督:望月智光/1988年/アニメ
 小学生の頃に大好きだったアニメの劇場版。早い話がラブコメのループを強制終了する話。恭介、まどか、ひかるの三角関係をいかにして終わらせるか? というテーマだけに内容はどんよりしてる。切ないね。ま、その気分を味わいたくて見たんだけど。
小学生の頃に大好きだったアニメの劇場版。早い話がラブコメのループを強制終了する話。恭介、まどか、ひかるの三角関係をいかにして終わらせるか? というテーマだけに内容はどんよりしてる。切ないね。ま、その気分を味わいたくて見たんだけど。
特に恭介から三角関係の終わりを告げられたひかるが、諦めきれずにストーカーっぽく振舞う部分がかなり切ない。「あの楽しかったラブコメをこんな形で終わりにしないで!」と胸を引き裂かれそうになった中学生の自分を思い出す。『ニュータイプ』に「ロードス島戦記」のキャラ絵を描いて投稿してたなぁとか、河原町のアニメイトに行ってたなぁとか、そんなアニヲタな自分をですがw それはさておき、大人になって見返してみると、この物語の展開にちょっとした疑問がわいてくる。
なぜ恭介とまどかはああいう形で三角関係を終わりにしようと思ったのか? しかも肉体関係はおろかキスもしてない状況で。ひかるはもともと恭介とまどかが好き同士であることを知っていながら、なぜ諦めきれずに執拗に恭介を追い掛け回したのか?
この部分はオレンジロードの枠を超え、ラブコメ的ループを終わらせて大人になろうとする二人(恭介&まどか)と、ループを終わらせたくないひかるという軸で考えると、見通しがよくなる気がする。実際、恭介とまどかはひかると距離をとろうとするが、ひかるは恭介を自分のものにしたとしても、三角関係そのものを終わらせたいと思っているわけではない。あの楽しかったループな日々を終わらせたくないわけだ。でも大人にはなる(アニメだからならないけど)。
そーいや望月峯太郎の『バタアシ金魚』の続編である『お茶の間』なんかもそういうの描いてたな。最近は切ないの好きかも。とはいえ『めぞん一刻』が円満なラストを迎えたとき、祝福と同時に物語が終わってしまうことに涙した中学生の自分も思い出すわけで。ループか…。音楽もループ好きだしな。うーむ。
この監督って他にも『めぞん一刻 完結篇』と『魔法の天使クリィミーマミ ロング・グッドバイ』もやっているそうな。ストッパーみたいな監督やね。次は『クリィミーマミ』か『ミンキーモモ』を見るかな。
Posted by Syun Osawa at 20:36
2005年04月29日
ZOO
乙一/集英社/書籍
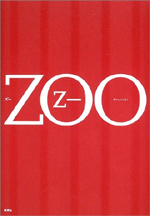 同書の作品がオムニバス形式で映画化された。その中の一本「陽だまりの樹」を神風動画が3Dアニメで作るというので予習の意味を込めてを読んだ。映画楽しみ…。
同書の作品がオムニバス形式で映画化された。その中の一本「陽だまりの樹」を神風動画が3Dアニメで作るというので予習の意味を込めてを読んだ。映画楽しみ…。
同書は1998年から2001年にかけて発表された短編によって構成されており、前半部分にはスニーカー文庫風のキャラ的側面が、後半にはミステリーやSFのファン達を意識した技巧的な側面が見え隠れしている。相変わらず読みやすい文体で、内容も面白い。後半の作品になるごとに僕の好きな乙一が少なくなっている気がするのだけど…単に僕がおぼこい作品に萌えるから癖があるからかも。
カザリとヨーコ
悲しい話。新劇調で昔懐かしいくらいに意地悪なお母さんが登場する。お母さんが双子の一人を可愛がり、もう一方を虐げる理由に「何で?」とはいかず、それを回避する方法ばかりに視線が向けられている。悲しい話やね。こういうのを読みたくて乙一を読んでいるとはいえ…。
血液を探せ!
トリックも面白く、キャラも立っている。主人公の強引な設定を使ってこういう面白い短編を書ける乙一は凄まじい。
陽だまりの詩
神風動画が3Dアニメ化した作品。この時点では神風作品は未見。乙一節炸裂の切ない物語で、人間不在の世界で人間を思う淡くて儚い様子が胸を締め付ける。一体全体、どんなアニメになるんだろうか? 期待ばかりが膨らんでゆく。
SO‐far そ・ふぁー
乙一の書く作品群はバラエティに富んでいるが、その中でもこういうラストを迎える作品が僕は好きだ。決して幸福な結末ではないけれど、「僕が生きているという事」についてのリアリズムが詰まっている気がする。
冷たい森の白い家
民話っぽい印象。そして相変わらず悲しい話。主人公が自分自身と向き合うとき、その周りの人間がこの話のように無造作に死んでいく感じは好きじゃないなぁ。
Closet
これも面白く読んだ。乙一の作品は基本的にすべて一人称で書かれているんだけど、ラストでその一人称の視点がググッと移る瞬間が素敵だった。
神の言葉
昔やったエロゲー『雫』を何故だか思い出す。あのゲームをプレイした当時はまだ学生で、初めてのノベルゲームだったこともあり、僕が受けた衝撃は凄まじかったが、今回はけっこう冷ややかに読んでしまった。んなこたぁない。
ZOO
タイトルが駄目だった。「ZOO」と聞くとどうしても「愛を下さい〜ウォウウォウ、愛を下さい〜ZOO」の「ズー」を思い出してよくない。主人公は動物園の看板を見るたびに自分が恋人を殺した事についての思いを深めるが、僕はこの言葉を聞くたびに辻仁成の悪い冗談を思い出してしまう。
SEVEN ROOMS
多摩美大のグラ展 でも似たような感想を書いたが、こういう作品に『CUBE』みたいって言ってしまう僕の言葉の浅はかさに問題がある。自分で小説を書いたりしないので、結局すぐに自分の経験から相対化して理解しようとする。悪い癖。僕はわりかし楽しんで読んだが、こういう作品群からもう一歩抜き出るラストを期待したい。
落ちる飛行機の中で
最初の禅問答のような会話はかなり妙で楽しかったのだけど、最終的な展開(つーか落としどころ)は平凡だったように思う。技巧一本でいくのか、心の問題を貫くのか、その辺がちょっと中途半端に感じた。
Posted by Syun Osawa at 15:58
2005年04月24日
週刊アニメ雑感 2005.04.24
今週はなんと言っても、gorillaz「Feel Good Inc」のミュージックビデオでしょうか。前から公開されていたらしいですけど。あと、ASK動画小組という中国のFLASHアニメグループの作品をまとめて観賞。プロフィール欄で「これまでのFLASHを越えるアニメーションを作ることが私の目標。中国のアニメーションの新しい構造は私達が創造する。」と息巻いている感じが心躍らせます。実際に見てみるとたしかにその匂いは少しある。
gorillaz「Feel Good Inc」
(wmv/7.28mb) web
by Jamie Hewlett & Alan Martin
日本のオフィシャルサイトの動画は哀れなくらい小さな画面なので、こちらの方が良いかと思います。。これは東芝EMIに限った事ではないんだけど、日本のレコード会社のこういう展開って本当に微妙だよなぁ。という事はさておき、ギターの弦のたゆみ方とかなかなか良いですね。あと雲がかなり美しいです。監督は『 Tank Girl 』という漫画の作者らしい。その漫画を読みたいよ、僕ぁさ。
積載
(flash/4.71mb) web
by ASK動画小組
プロ? っていうか、アニメ学校の生徒の作品? 『十面埋伏』からクオリティをさらに上げてますね。背景もしっかり描けているし、アクション一本で攻めていた前2作に比べて抑えが効いてます。さらなる進化を遂げるのか、中国版Ninjai Gangになってくれることを密かに期待しております。
引爆激情
(flash/3.97mb) web
by ASK動画小組
ストリートバスケの動きを丁寧に描いている。こういうアニメを描きたいなぁ。最後はダンクで決めてほしかったw そーいや中国ってバスケ強いんだよね。前にNHKで特集組まれてた15歳くらいの中国の天才バスケ少年はその後どうなったんだろうか…。
十面埋伏
(flash/6.23mb) web
by ASK動画小組
前に紹介したこともある忍者モノ。これがたしか処女作品だったと思います。ここから上に上に行こうという意気込みが良いですね。あと、映像のクオリティも凄いんですけどエンディングの曲もなかなか素敵だったりします。
スーパーマン/メカニカルモンスターの巻
by Dan Gordon/1941年
宮崎駿作品に登場する巨神兵の原点。この作品を見たのは実は今回が初めて。あまりに動きが滑らかで驚いた。なおかつ演出が素晴らしい。ロボットの不気味さを影で表現するなど、日本が太平洋戦争に突入する頃に、すでにこのクオリティの作品が作られていたことにただただ感動。
おもちゃの国(Santa's Workshop)
by Wilfred Jackson/1932年
子どもの夢がアニメーションに見事に表現されている。よく見ると横向き歩きで足が滑っていたりする。船のオモチャの小窓から人形が次々と顔を出すシーンをはじめ、とにかく「モブ」の動きが素晴らしい。自分で描くことを考えるとゾッとするが。
Posted by Syun Osawa at 23:31
-Nから第二弾EPリリース
Scatter Stars by Andrey Kiritchenko
日本発のネットレーベル-Nから第二弾EPがリリースされました。メッチャ渋いです。最近、本屋で『電子音楽 In The<Lost>World』という本を見つけ迷いました。こういう近道は必要なのかどうなのかと。毎日ACOWO と artistserver.com の新着を追っているだけで音楽を十分に堪能してるし、そういう流れの中で『 Scatter Stars 』とも巡り合うわけです。こういうのは“縁”ですね。それが日本人的結論です。
第三弾では 第一弾 に続いて、大沢がカバーFLASHを作成する予定です。
Posted by Syun Osawa at 21:46
2005年04月21日
太陽の塔
森見登美彦/新潮社/書籍
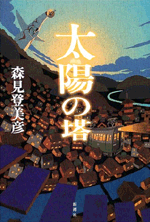 京都の地名がふんだんに散りばめられた地方出身の京大生が描く「その周辺のファンタジー」という感じ。地方ネタ&ファンタジーというのは流行なんでしょうか。よくわかりません。ストーリー的にはモテない大学生が斜めに世間を見ながら送る日常生活を語っている、というだけの話。京大生という関西ではそれなりに高いプライドが、魚の小骨のように一生喉に刺さり続けるであろう事を自覚しながらも、結局はたわいもない事に悩み続けている自分について言及している(もちろん作者=主人公という意味ではない)。
京都の地名がふんだんに散りばめられた地方出身の京大生が描く「その周辺のファンタジー」という感じ。地方ネタ&ファンタジーというのは流行なんでしょうか。よくわかりません。ストーリー的にはモテない大学生が斜めに世間を見ながら送る日常生活を語っている、というだけの話。京大生という関西ではそれなりに高いプライドが、魚の小骨のように一生喉に刺さり続けるであろう事を自覚しながらも、結局はたわいもない事に悩み続けている自分について言及している(もちろん作者=主人公という意味ではない)。
「みんなが不幸になれば、僕は相対的に幸せになる」
宮台真司は サブカル「真」論2 で「今の大学生は、モテないということがルサンチマンではなくなった。」と言ってたけど、まだそれを真正面からやってるヤツがいるんだなぁ…なんて雑な感想を抱きながら読んでいたら、あまりにストレートなラストだったもんでちょっと泣けてしまった。
つまり僕は彼女が好きである。
これ以外にないわけで。こういうベタに立ち戻れるファンタジーはやっぱし強いと思う。しかしまぁ、彼の小骨はこんな程度のラストではなかなか取れる事はないだろうけど。
この本を読んでたら、不覚にも京大出身だった高校の担任を思い出してしまった。なんでか知らないけれど文章の雰囲気が凄く似てる。例えばそれは、学級新聞に『究極超人あ〜る』の「…と思ふ」的な言葉を多用していて、かなりハズしていた記憶とか。もしかしたら京都大学には「京都弁」ならぬ「京大弁」なるものが存在するのかもしれない。
Posted by Syun Osawa at 22:27
2005年04月17日
週刊アニメ雑感 2005.04.17
最近、同人誌用にFLASHアニメ紹介記事を4枚書いたんですが、その時に製作者の裏取りで新しい発見がありました。UNIT9のテクニカルディレクターBen Hibon氏のホームページの存在。知りませんでした。今回は彼の公開している3Dアニメに尽きます。あとは『 NITABOH 』など。
Darkglobe「Break My World」
by Ben Hibon web
カッコイイ、カッコイイ、カッコイイ、カッコイイ、カッコイイ!! あー、大好きです。Darkglobeの「Break My World」って曲のミュージックビデオなんですけどね。セル系の3Dアニメなんですけどね。イギリス産なんですけどね。とにかくENTERから入って上から三番目をクリックして、PLAYボタンです。音楽も良いです。
よーするに、戦争に行くんですよ。軍国少女の話です。でも心は置いてくんです。その表現がヤバいくらいカッコよろしいです。なんでこんなにカッコイイのかと思ったら、この人「 full moon safari 」を作った人なんですね。もう超納得です。
ぽわぽわ宇宙大冒険
キャラクターも可愛いし、話もほのぼのとしてあったかいし、それでいてよく動くし。作者の気持ちがビシビシに伝わる素晴らしいFLASHアニメです。ロケットが星を回っていくところとか、捉えている視点は高いところな気がするので、次回作も本当に楽しみです。
Monkey PIT
(mov/01:11s/10.3mb) web
by Jeff Fowler
動物園の猿がサングラスと戯れるショートフィルム。キャラクターの表情豊かな動きが素敵ですなぁ。こういうの見ると3Dがどんどん羨ましくなってしまう。けのフサフサ感とかどうやって出してるんだろう…。
罠
(wmv/08:29s/13.3mb) web
by 生命体8471
超久しぶりに涙の少年剣士を見たら3Dバージョンの方が凄い事になってた。たぶんかなり昔のモノなんだろうけど、エフェクトとか凄いねぇ。この人はFLASHアニメも凄いし、セルシェードの3Dも凄いしで学ぶところが多過ぎる。Ben Hibon氏もそうだけど、こういう多角的な表現者の魅力ってあるな、絶対。僕的には日本で一番勉強になる人かも。
日本一桃太郎
by 山本早苗/1928年
どこかで見た記憶が…。動きそのものはそれほど感動しない(切り抜きアニメと考えれば凄いが)。ラストで桃太郎一家と戦いに敗れた鬼たちが横向きに歩いていくシーンはかなり素敵な雰囲気が出ている。
流行はベティから(Keep in Style)
by Dave Fleischer/1934年
衣装や物体が次々と変化する。機械的なモーフィングにはない味がある。固定カメラで人間の動きをコミカルに捉えたアニメーションは絶品。
Posted by Syun Osawa at 15:00
NITABOH 仁太坊−津軽三味線始祖外聞
監督:西澤昭男/2003年/アニメ
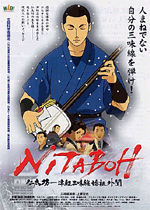 津軽三味線の発祥の物語を題材にしたというところがツボで、密かにずっと見たかった作品。小学校のときに体育館で見た『はだしのゲン』とか『11ぴきのねことあほうどり』みたいに、学校とかを中心に上映されているらしく、世間的には知る人ぞ知るという感じかも。
津軽三味線の発祥の物語を題材にしたというところがツボで、密かにずっと見たかった作品。小学校のときに体育館で見た『はだしのゲン』とか『11ぴきのねことあほうどり』みたいに、学校とかを中心に上映されているらしく、世間的には知る人ぞ知るという感じかも。
うーむ。それにしてもまとも過ぎやしないかい? 物語はとっても好きだし、三味線での対決がクライマックスというのも大好きな展開ではある。とりあえずプロットを簡単にまとめるとこんな感じ。
ヒロインとの出会い→仁太坊失明→失望→三味線と出会う→父の死→ヒロインとの別れ→(7年後)→流しの三味線で生計を立てている仁太坊→三味線で行き詰る→ヒロインとの再会→太棹(弦の太い三味線)との出会い→使いこなせない→イタコ修行→天才・田原坊との対決
時系列に沿ってすんごい真っ直ぐ話は進む。失明から津軽三味線で対決するところまで完全順送り。ただ順送り過ぎるから、いきなりイタコが出てきたり、天才・田原坊が出てきて「何だ?」となる。こういう映画に『寅さん』的なベタを期待する僕としては、感動したいわけですな。そうしたら間違いなく田原坊が冒頭で仁太坊を叩かなきゃならんわけで。その天才を倒すために津軽三味線を編み出すんですよ。いきなり最後に天才・田原坊って出てこられても…。しかも美男子だしw
太棹を弾きこなせない仁太坊がなぜか突然イタコ修行をするとか、挿入歌が加藤登紀子の娘が歌う場違いなポップソングなところとか、僕的にはツボに入って、そういう意味ではかなり楽しめたんだけど。ただそういうB的楽しみよりも、もっとストレートに感動したかった次第。
ちなみに脚本・監督の西澤氏って株式会社ワオ・コーポレーションの社長だったんですね。次回作も社長自ら脚本・監督をやるって言うんだから大神源太会長が主演した『ブレード・オブ・ザ・サン』…ウソウソ。アニメーションの学校も経営されているらしいので『風の名はアムネジア』のノリに近いのかもしれない。
Posted by Syun Osawa at 13:26
2005年04月14日
網状言論F改
東浩紀編著/青土社/書籍
 この本については、ネットで唐沢俊一氏らが過剰反応したという事くらいしか知らなかったので、以下の流れでちょっとだけお勉強。
この本については、ネットで唐沢俊一氏らが過剰反応したという事くらいしか知らなかったので、以下の流れでちょっとだけお勉強。
『 郵便的不安たち 』(朝日新聞社)
オタクから遠く離れてリターンズ
1998年の伊藤剛氏と東浩紀氏の対談
Eの呪い
竹熊健太郎氏が岡田斗司夫氏を皮肉った小説
『国際おたく大学』(光文社)
唐沢俊一氏が書いた「サブカルのパンドラの箱〜伊藤(バカ)くん問題」が裁判に発展。たしかにレベルの低い悪口ではあるけれど、愛情が反転したというか、可愛さ余っての部分が大きかったからこういう自体になったんではと勝手に思う。
伊藤さんの物語
ライターの伊藤剛氏と唐沢俊一氏の戦いが中心だが、何となく当時の雰囲気を一番よく書けているような気がする。(8pt横組みにして刷り出したら70ページを超えた。スゲ)
見る阿呆の一生 特別編
竹熊健太郎氏のロングインタビュー(今は本になった模様)
『網状言論F改』に関するネット上の言説たち
唐沢俊一氏の裏モノ日記など
唐沢俊一氏の「悪口」について
『網状言論F改』に対する唐沢俊一氏のコメントに対する返答
『エヴァ』が始まったのが1995年ですから、もう10年も経つんですね。00年代も半ばに差し掛かってるので、もはや80年代がどーとか、90年代がどーとか言ってられません。
全体を大雑把に眺めて、東浩紀氏が1998年に「 オタクから遠く離れてリターンズ 」でコミケの事務局に対して言ってたことと、2004年末に自作のプラカードを持ちながら「『美少女ゲームの臨界点』の新刊こちらでーす!」と同人誌の客引きしていた様子が自分の中で上手くかみ合わず、なんとも不思議な気分になります。ミイラ取りがミイラになったのか、それともトロイの木馬を仕掛けるつもりなのか僕にはよくわかりません。あと、伊藤さんの物語 は2005年に無知な僕が読むんだから、たしかにロゼッタストーン的な役割を果たしてます。
という前置きをさておき、とりあえず『網状言論F改』に関しては、どの文章も楽しく読みました。敵対的な物言いなども意外に少ないし、みんなマジメに何かしようとしてるのが伝わってきましたから。ただ気にかかるのはオタクを語ってるのに「マジメ過ぎる」こと。頭が良い=人を楽しませるのが上手ではないんですね。当たり前か。
話変わりまして『エヴァ』の話へ。竹熊健太郎氏が「 見る阿呆の一生 特別編 」の中で「オタク密教/顕教」という言葉を使って以下のように語っているのが印象的でした。
「『エヴァンゲリオン』は、「顕教」が「密教」に宣戦布告した作品なんだよね。」
密教と顕教の違いは詳しくわかりませんが、「顕教=本気で〈萌え〉る人」と「密教=あえて〈萌え〉てるような態度をとる人」という感じでしょうか。今の「セカイ系」につながる、えらく糞マジメで陰鬱な雰囲気の作品を是とする雰囲気や、そのあたりの人たちを「オタク」と定義してしまう風潮は、竹熊健太郎氏が言うところの「顕教」な人たちが牽引しているのかもしれません。
『網状言論F改』では「オタク」の定義に終始しすぎて話が噛み合っていません。ただし、とにかく思いの丈を述べ合って、ここを始まりにしようというような熱気は感じられます。先代のオタクが築いてきたものをアカデミックに整理して、新しい社会に生かそうみたいな事にみんなかなり本気です。たしかにそういうマジメな態度は学校の先生は褒めてくれるに違いありません。そしてそれは、大学に漫画やアニメに関する学科ができるとか、日本マンガ協会のような学会ができるとか、アニメ製作に国が予算をつけるとかそういう事なんでしょう。
で、そうやってカッチリ固めたとして、その先に何か見えてきますかね? 自由な創造空間が広がってるのですかね? ネットの世界でバカFlashが流行するのなんて、まさにそういった糞マジメさに対するカウンターだと僕は思いますけど。漫画やアニメを文学をそうしたように殺しにかかっているようにしか見えませんませんけどねぇ。僕には。
Posted by Syun Osawa at 23:47
2005年04月12日
me and a gun (xerxes 2004 remix)
(7:17s/mp3/10mb) download
by xerxes
Tori Amosの「me and a gun」という曲のRemixモノ。Chillout系のRemixをネット上でなかなか見つけることがないので、そういう意味でも貴重な一品。ボーカルの最大の魅力は、ボーカルが良ければ演奏者の良し悪しとかが関係なくなってしまうほど存在感を持ってしまう点。この点は雇われキーボード奏者さんが僕によく話してたことですが、これを聴くと結構納得できます。それだけ抑えの効いたRemixをxerxesがしているということなのかもしれませんけど。
ちなみにfive musiciansが2000年にリリースした『 two years 』というコンピレーションに収録されているNecrosの「amber poison」に代表されるように、勝手Remixはある意味でMOD時代の遺産的存在。まぁ著作権的な話になると微妙っちゃあ微妙ですが、それを言ったら今のターンテーブルの音楽は成り立つのかって話にもなるわけで…。いずれにせよ女性ボーカルモノのマッタリRemixが好物というだけの話だったりします。
Posted by Syun Osawa at 22:16
2005年04月10日
週刊アニメ雑感 2005.04.10
今回は東京アニメフェアで公開された アヌシー国際アニメーション映画祭 2004 の受賞作品と CREATOR'S WORLD 2005 の作品から数点。あと海外からのパロディアニメの秀作などの感想。一番のオススメは「カニの革命」という作品。こういう批評性とユーモアと技術力をすべて兼ね備えた3Dは、日本の3Dアニメ界ではなかなかお目にかかれないので一番オススメしたい。あと「チャーリー・ブラウン」に関しては、日本でも70、80年代に学生だったアニメーターなら似たような作品を押入れにしまってるんじゃないだろうか。
Bring Me the head of Charlie Brown
(mov/03:20s/33mb) web
by Jim Reardon
『シンプソンズ』のディレクターを長年務めたJim Reardonが学生時代に作った自主製作アニメ。モノクロのためかなり古いビデオに見えるが、実際は1980年代後半に作られたものらしい。無意味に残虐なのはアメリカ特有の悪ノリだろう。
とはいえ彼が後に『シンプソンズ』のディレクターになるんだからそれはそれで頷けるし、チャーリー・ブラウンがオリジナルのような動きを見せていることから製作者の腕が「並」ではないこともわかる。少し前に海外のFLASHアニメ界を席巻した『Happy Tree Friends』も含め、こういった残虐性の系譜というのはアメリカ文化の中に脈々とあるんだなと再認識させられた。もちろんあのコロンバイン高校事件も含めて。
Mountain Dew "Spy vs. Spy"(全4話)
日本でもお馴染みのジュース「マウンテン・デュー」のCM動画。王道の対決モノ。実写と3Dの使い方もシンプルだし内容もわかりやすい。こういう作品は本当に好き。
痴漢は犯罪! デモムービー
(mpg/01:46s/78.6mb) web
by FULLTIME
エロゲーのデモムービー。新海誠氏をはじめインディーズのアニメ作家さんはなぜかエロゲーと親和性が強い。このムービーはそういった話とは関係ないんだけど、セル系3D(トゥーンシェード)のキメが細かく、2Dへのアプローチっぷりが尋常ではない。最低な内容とは裏腹に『プラトニックチェーン』や『アップルシード』の次の領域(もちろん技術的にという意味で)へ入った作品を見た気がした。この流れで同作品を3Dエロアニメ化してくれるのなら、僕もTSUTAYAへ足を伸ばすかもしれない。
Posted by Syun Osawa at 00:34
アヌシー国際アニメーション映画祭 2004
会場が例年と違っていてちょっと焦った。東京アニメフェアの上映会はアヌシーの作品など海外の秀作アニメを見ることのできる数少ない場なので、今後も絶対に続けてほしいと思う。
Birthday Boy
Sejong Park/2004年/韓国
米アカデミー短編アニメーション部門賞にノミネートされた作品。親が戦争に行っている軍国少年の様子を淡々と描いている。モブ(群集)の少なさをカバーできる素晴らしい題材だし、一人で戦争ごっこをする軍国少年の様子が戦争の虚しさを一層際立たせている。とくに戦車を載せた列車が通るシーンは秀逸(どこかで見たような気はするが…)。今だからこそ問題意識を持って眺められる作品だと思う。寂れた村の様子も素敵。
No Limits
Heidi Wittlinger、Anja Perl/2004年/ドイツ
鉛筆でザザッと描いたような筆感残しまくりのモデリングが魅力的。ようはこういうことらしい。「世の中はなんでもありだ。でも子ども達には限界がある。ストップ児童労働!」
La revolution des crabes
Arthur de Pins/2004年/フランス
アヌシー国際アニメーション映画祭で観客賞を受賞しただけのことはある。最近見た作品の中では群を抜いて面白かった。「カニの革命」と名づけられたこの作品のあらすじはこうだ。カニは方向転換ができない。だから生れた瞬間から自分の進むべき方向(左右)は運命付けられてしまう。そんなカニの中の一匹があるとき革命を起こす。オチもシュールで渋い。3Dあり手描きありで暖かな映像も魅力的だった。韓国系よりもフランス系の3Dの方が好きだなぁと改めて実感。
Lorenzo
MikeBabriel/2004年/アメリカ
ディズニー作品。アヌシー国際アニメーション映画祭グランプリ作品…なんだけど。そしてキャラクターの動きも凄いんだけど。うーむ。ネコと人格のあるネコの尻尾の話。音楽にあわせて踊るネコの様は古き良きディズニー作品を連想させるし、アニメーションのクオリティも群を抜いてはいるんだけど、うーむ。少なくとも示唆的ではないよな。
Posted by Syun Osawa at 00:32
2005年04月09日
CREATOR'S WORLD 2005 in 東京アニメフェア
東京アニメフェアの中の個人作家ブースはいつも面白い。それは「個性的な作品が並んでいる」とかいう話とは関係なく、個人製作の作品をお金に換えるための試みが作家によって様々で、みんなの模索している感じが面白いのだ。そしてこういう場では「ニート!」のような消費されて消えていくだけの一発ネタがやはり強い。これは単にサウスパーク系のアニメネタを個人レベルで反復しているだけなのか、はたまたそれとは別の次元で大きな変貌を遂げるのか。『ヤングサンデー』の「おしゃれ手帖」だけを毎週立ち読みしていたあの日の気分で動向を眺めている。
Hai and Low
by 森下征治
キャラクターが非常に上手い。おぼこくない。東浩紀がフランス現代思想をやる人は、最後には日本語を離れてフランス語で思考しそのように語る、というようなことを言ってたけどまさにそんな感じ。日本とか関係ないし。こういう人には『ラピュタ』のシータが言った「土に根をおろし〜」の名台詞を胸に焼き付けてほしいもんだ。森川耕平氏の『NATURAL』のアプローチに近いと思ったけど、こちらの方がフランス寄り。
Recover the Sky for Tokyo System
by 東和信
空間とか建築とかそういう方面からのアプローチなんでしょうかね。僕には少し難しい。中央のキャラクターはマネキンで、背景の変化の方に焦点を当てている。壁から天上を走る炎の映像など非常に洗練されていて深いのだが、いかんせん飽きた。
USAO!
by 田上公雅(Orange Project)
Macintoshのデスクトップイメージを3D化し、その中に住むポストペットをパロった作品。寝ているクマを起こそうとしている矢印がマウスのポインターをイメージしている。最後の「貞子」まで、かなりコンセプトに誠実に作られた印象を受けた。それがいいかどうかはよくわからん。
asobo
by 日下部実
クレイか3Dかわからないようなモノクロの空間が、不思議な世界を作っている。さらにシンプルな音楽と、ミニマル感漂うシュールなギャグが合わさってかなりのインパクトがあった。一番お気に入りのシーンは、ピョンピョンと飛び石の上を飛んでいるキャラクターが、着地する瞬間に地面が無くなり、奈落の底へ落ちていくシーン。あのミニマル感は秀逸。
Posted by Syun Osawa at 23:58
2005年04月08日
郵便的不安たち
東浩紀/朝日新聞社/書籍
 この本を読みたくて、ずいぶん遠回りした感じする。哲学とオタクの要素が分け隔てなく並べられ、それらを僕のような素人に向けて丁寧に説明しているところが好感を持てるし。注釈の一生懸命さに著者の熱い思いを感じる。インテリがどうとかそーいうのではなく、もっと若々しい青春みたいなヤツを…。
この本を読みたくて、ずいぶん遠回りした感じする。哲学とオタクの要素が分け隔てなく並べられ、それらを僕のような素人に向けて丁寧に説明しているところが好感を持てるし。注釈の一生懸命さに著者の熱い思いを感じる。インテリがどうとかそーいうのではなく、もっと若々しい青春みたいなヤツを…。
ところがどうしたことか、東浩紀のイメージがなぜか土田世紀『編集王』に出てくる明治一郎というキャラクターと被るんだなぁ。よーするに嫌なヤツ。嫌なヤツになっちゃった元良いヤツ。その原因は「うる星やつら」おたくだった東少年が書いた「ソルジェニツィン」に関する論文を、柄谷行人に
「東君、あれ面白いから『批評空間』に載せます」
と言われ、哲学者/批評家としてデビューを果たした後、大衆受けしない『批評空間』と上がらない自分の知名度に業を煮やした著者が
いまや、読者は確率的にしか見つからない。だから、ばら撒くことがすべてです。パルコやリブロでワゴン売りさせるためにはどうすれば良いか。アニメ論を書くしかない。
というスタンスでアニメ論やってきたからなのかなと。そもそも彼が研究してきたデリダについても
デリダについての著作を喜んで読むというのは、だいたい僕のイメージとしては、日本で千人、ヨーロッパで二千人、アメリカで二千人、それで終わりです。
と言っているわけで、そうすると彼が唐沢俊一に反論した「 唐沢俊一氏の「悪口」について 」で言っていることと矛盾する。そういう微妙な発言のズレもあって、この本の中から感じられる東浩紀の熱い部分は凄く共感しつつも、学生時代「ラムちゃ〜ん」と言っていたヤツが、エリート街道を歩むなかでどんどん嫌なヤツになっているようにも映ってしまう(ただその印象は、2004年の同人活動でちょっと変わったけど…)。
あと『エヴァ』ブームにまったく関心がなかった僕にとって、そこでブレイクした人たちはとても「糞マジメ」な印象があって、例えばこの本の中に収録されている文芸批評なども悲壮感があって僕的にはちょっとしんどい。竹熊健太郎みたいにギリギリ距離をとりながらの人はいいけど、その下はやたら真剣でちょっと引いてしまう。それは『網状言論F改』の話か。ちなみに、あとがきで東はこんなことを言っている。
僕が本当に望むのは、その名が匿名となること、つまり、もはや著者名とは無関係に、『存在論的、郵便的』と『郵便的不安たち』という二つの異なったタイプの本が読まれ、たがいに交わり、そしてそこから無数の子供たちが次々と生まれることだ。
この二つの本を読み込みこなせる子供といったら…。それこそ 好き好きお兄ちゃん! のkagami氏じゃないですか!
Posted by Syun Osawa at 00:49
2005年04月06日
presets
(4:40s/mp3/6.42mb) download
by xerxes
今回もxerxesです。この曲は日本でもお馴染みのネットレーベルCamomileからリリースされました。沁みますね。仕事やらなんやらで疲れているときはxerxesを聴くにかぎります。PCで丸みがあって優しい(しかも特徴的な!)音作りをできる素敵なComposerです。中盤以降、この曲が語りだすまでの間と、そして空間にヤられました。こういう人がMOD界隈でウロウロしていたことを嬉しく思いますね。次回もxerxesです。tori amosの勝手にRmixモノです。
Posted by Syun Osawa at 02:08
2005年04月03日
週刊アニメ雑感 05.04.03
ウィンザー・マッケイなど古いものは相変わらず作り手の根性を感じる。今はそれを機械がカバーしてるので僕のように日和(ひよ)ってアニメを作ることも可能になった。中国や韓国あたりでは、FLASHアニメのジャンルでそのあたりが上手く化学反応を起こしているように思える。特に中国は著作権意識が薄いので、有名人の曲を無断で使用したMTV作品が続々と公開されており、芸術的な可能性としては興味深い。あとは多摩美の卒展で話題となった『BIBLIOMANIE』など。高速紙芝居は新たな可能性かも。
虫のサーカス
ウィンザー・マッケイ/1917年
竹熊健太郎さんのブログでマッケイの動画が公開されてましたけど、あれよりもいいですね。一番難しいと思われる背景固定のアニメーションをこの時期にやってしまってるんだから凄い話です。おじさんが木陰で昼寝し、そこで見る夢。夢の中の劇場に観客としてのおじさんの頭が映っているのが面白い。しかもそれが最後のオチに効いており、ショートフィルムとしての構成力も非常に高いと思う。
動物曲芸団
ハーマン・アイジング/1932年
もちろん白黒アニメ。この頃のアニメはたぶんセルじゃなくてペーパーなのかな? それにしても動きが凄まじい。しかも音楽と見事にテンポがあっていて、パソコンもない時代にどうやってこれを作ったのか不思議で仕方ない。ブラックユーモアも効いてる。
BATMAN New Time
(mov/11:58s/73.8mb) web
by Jeff Scheetz & William Vaughan
DAVE Schoolという映像学校の制作による「バットマン」物。レゴ風の3Dアニメを採用している。顔の表情は平坦な顔の上に直接描いているような形でつけており、これはこれでかなり安定感がある。さらにストーリーの方もしっかりしており、オリジナルなのかパロディなのかは知らんけど、ちゃんとバットマンしていた。日本でもこのクオリティで「ガンダム」とかのパロをやってくれるといいのになぁ…。
朋友 ただあなただけを見つめて
(flash/3.6mb) web
by the4world
これ誰の曲だったかなぁ…。かなりいい曲なんだけど。Didoかなぁ…。それにしても、中国系列のFLASHは相変わらずクオリティが高い。彼らが使用するアニメ絵の源流が日本にあることだけで、石原慎太郎の気持ちよい日本語りにあぐらをかいてはいけない。先日、何かのニュースで中国人の6割がアメリカに対して好感を持っていると言うのがあったが、それは中国のFLASHアニメを見ていれば嫌というほどわかる。国家レベルでの歴史認識の摩擦とは関係なく、文化レベルにおいてはかなりディープな人間の嗜好が国家とは関係のないところで絡み合ってしまっている。そして作者のプロフィールにはプレステ2が鎮座している。
とか言いつつ調べてみると、やっぱりこの曲Didoでした。Didoの「Life For Rent」という曲。公式ホームページの 試聴ビデオ が相当エロいです。日本のフェミニストは頭いいしか取り得ないけど、北アメリカ大陸の人はサラ・マクラクランを筆頭に、美しくエロいです。
Cake Dance
(flash/7.43mb) web
by amalloc / SamBakZa.net
韓国系FLASHアニメ。かぼちゃワイン(古っw)の時代を彷彿とさせる王道のアニメーション。かなり素晴らしい出来です。設定が明快なことも手伝って、気持ちよく作品世界に没頭できる。彼女の誕生日にケーキを届けたいという主人公の思いと、そこに待ち受ける困難の数々。こういうアニメは本当に強い。韓国産、中国産のFLASHアニメのクオリティは相変わらず高いです。
ちなみに、この作品だけ見ると彼女(ウサギ)と彼(ネコ)の関係はわからない。これをより深く知るためには前作を見なければいけない。というわけで、前作は以下。
There she is!
(flash/2.70mb) web
by amalloc / SamBakZa.net
彼(ネコ)を追いかける彼女(ウサギ)の関係がよく描けています。追いかけられすぎてうんざりしているんだけど、少し心惹かれる部分もある。まさに『うる星やつら』の世界ですね。まぁ、パクリと言えばパクリ。ただそれを言ったら、いま日本で活躍しているクリエイターもみんな先人のパクリって事になってしまいますw とりあえず気合の入っている動画パートに、作画勉強中の筆者としては大いに刺激を受ける作品。
Believe
(mov/04:23s/31.4mb) web
by Dom & Nic
ケミカルブラザーズのプロモーションビデオ。ケミカルのプロモはいつも好きなんだけど、今回は妙にタモリ倶楽部っぽくて微妙。実写と3Dを融合した映像って、それ自体はもう完全に違和感とかなくなったみたい。
もジャ魔女ED
(flash/1.46mb) web
by 蚤様
『おジャ魔女どれみ ナ・イ・ショ』というテレビアニメを2ちゃんキャラでパロディ化したものらしい。元ネタを知らないのでどこまでがオリジナルなのかわからんけれど、キャラクターを丁寧に動かしていてる。2ちゃんキャラのアニメって、たまにこういう高いレベルのものが登場するから不思議ですな。僕の中ではその最初(ダウンロードしてCD-Rで焼いたという意味で…)が 512kb さんだったりするわけですが。
Posted by Syun Osawa at 18:06
多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業制作展 2005
長いタイトルですね。全体を通しての感想は、とにかくみんなアッパーだなぁって事。アッパーもアッパー、超アッパー。きっと自分とその周辺のこと以外は眼中に無いんだろうなぁとか、年金とか選挙とかどうでもいいんだろうなぁと思わせるアッパーさなんだけど、そのアッパーさがインディーズアニメ界を牽引していることは間違いない。さて。
BIBLIOMANIE
by 藤田純平
大人気でした。30分越えの超大作にも関わらず、時間の配分が上手く一気に見ることができた。物語的には後半はかなり急いで進むんだけど、あそこでネタ明かしを丁寧にやったんではたぶんダレたんじゃないかな。一気に見せたのは正解だと思う。そのへんの客を意識した作品の作り方は才能というヤツですか。あと、この作品の核とも言える「ゲームの部屋」での漫画や格闘ゲームを意識した映像作りは秀逸。あれを『フリクリ』を見ないで作ったとすればなかなか凄いと思う。こもれ才能か。たいしたもんだ。
とはいえ、この作品は僕の好きな狭義のアニメではない。どちらかと言うと「高速紙芝居」という新しいジャンルではないかと思える。テンポと音楽とキャラクターで物語を作っていく。画面は常に動いている(このあたりはFLASHアニメ作家の森野あるじさんに近いかも)という感じ。中割り部分を客が脳内で補完してくれるんだから無問題。そこを突っ込むオタもいないだろうし(僕くらいか)。エンディング曲とか客ウケを狙いすぎな気がしますが、全体通して素晴らしい内容。それにしてもアッパーですね。
よるとり
by 田中由香利
全体通して、一番心に残ったかも。この手の温かいアニメって、紙芝居状態のものが多いけど、これは丹念に作っていて凄く沁みる。
Go to school
by 宮内亜美
作品としては今回の卒展で見た作品群の中では一番楽しんだ。このノリはアッパーの中でも好きな部類。今は無きアメリカン・ショートショート的なコメディ。
room_runner
by 波多喜一
最初3Dかと思ったら、かなりヘタだったんで手描き(トレース?)なんだと思う。真相は不明。そこでちょっと愛着が湧いた。こういう作品を見ると、すぐにナイキのCMとか『CUBE』みたいって言ってしまう僕の言葉の浅はかさ自体に問題がありそうなので、感想を書きづらい。気合入っている作品は何しろ好き。
Posted by Syun Osawa at 17:54
2005年04月02日
ヘヴィメタル FAKK2
監督:ミシェル・ルミール、マイケル・コールドウェイ
2000年/アニメ
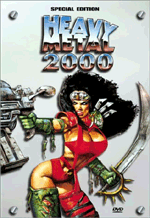 名作『 ヘヴィメタル 』の名前を冠につけてはいますが、続編によくあるダメダメ感がどアタマから伝わる微妙な作品。絵はたしかにそれなりに綺麗だし、ふんだんに3Dを取り入れてはいるんですけどね。それとアニメの面白さは別なんだという事を今回はっきりと思い知らされた気がします。
名作『 ヘヴィメタル 』の名前を冠につけてはいますが、続編によくあるダメダメ感がどアタマから伝わる微妙な作品。絵はたしかにそれなりに綺麗だし、ふんだんに3Dを取り入れてはいるんですけどね。それとアニメの面白さは別なんだという事を今回はっきりと思い知らされた気がします。
世界観のダメダメっぷりは前回の方が凄いんですけど、それは愛すべきダメダメっぷり。こっちはサントラのヘヴィメタだけが威勢がよくてそれが悲しいくらいに空回りしています。
そもそも物語発動の動機が「絶大な力を手に入れたタイラーがこれといった根拠もないままにある星を滅ぼし、帰りがけに美人姉妹の妹を連れて行く」というところにあったりするので、その辺は愛すべきと言えば愛すべきなんですけど。残念ながら今回は前作の廃れた感じがほとんど出ていなかったので、アウトローアニメとしてはB級(意味不明)かなぁと思います。とはいえ愛すべきダメさが全くないわけではなく、例えば鋼鉄の手錠で繋がれた妹を姉が助けるとき、なぜか素手で簡単に外してしまうところとか清々しいですw
ちなみに、この微妙な作品が作られたキッカケは、同名のグラフィック・ノベル誌『ヘヴィメタル』を買収したケヴィン・イーストマンが美術監督としてクレジットされているあたりにあるらしいのですが…真意の程はわかりません。
Posted by Syun Osawa at 21:55